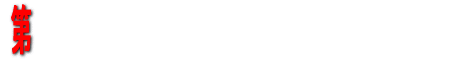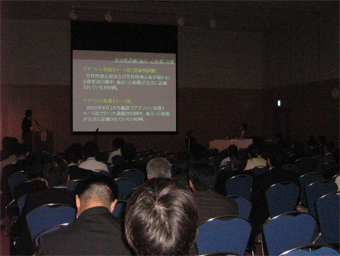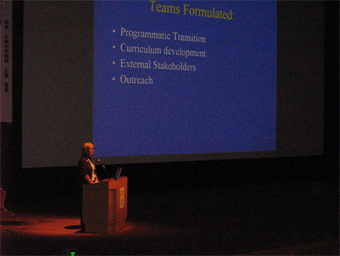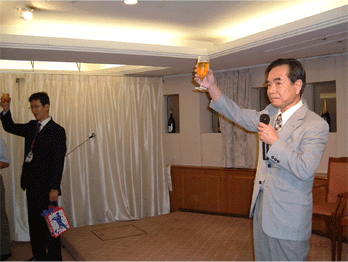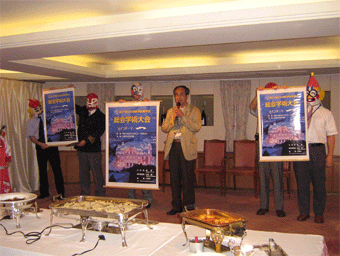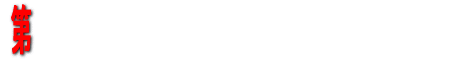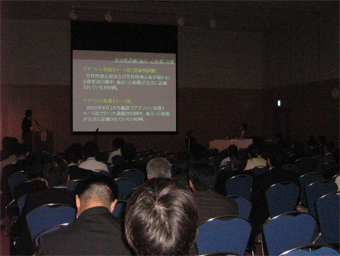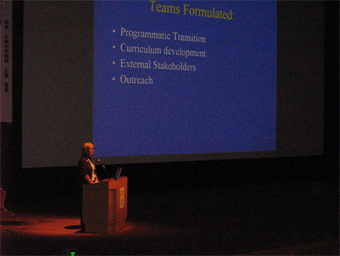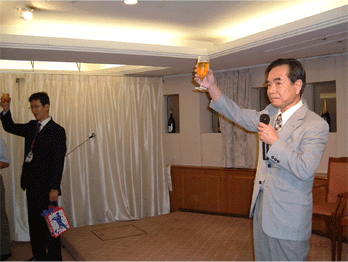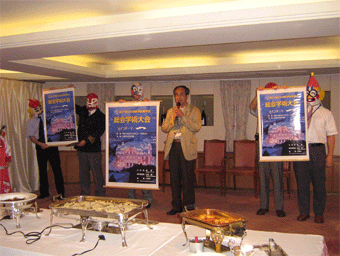|
第26回日本核医学技術学会総会学術大会は7月22,23の両日、福岡国際会議場で開催されました。梅雨明けが遅れ、鹿児島では犠牲者が出るほどの大雨が続いており、九州南部からの列車に運休が相次ぐ中、関西方面からの新幹線は順調で博多駅に着いたときには幸いにも雨は降っていませんでした。
私にとって今回の総会学術大会は来年の大阪大会の準備もあり、会の運営を中心に見学させていただきました。一般研究発表では過去最高の99演題ものエントリーがあり、それを3会場でどのように運営されるか注目していました。結果的には6月30日までにスライドデータを提出するシステムにしたことで発表者のスライド受付もスムーズになり、運営側も事前に動作確認をすることができたため、1日目に54演題、2日目には45演題の発表がトラブルもなく行えたと思われます。個人的には直前までスライドの手直しをしたいですが、運営を考えると仕方がないと思います。一般演題では、昨年秋にFDGのデリバリーが開始されて始めての学会なので、デリバリーFDGを使用したPET検査の演題が多く、会場にはたくさんの聴衆が詰めかけていました。初日の午後からは、海外招待講演としてSNMTのValerie R. Cronin会長と韓国から第9回世界核医学学術大会の広報として次期大韓核医学技術学会長の金 昌浩先生の講演がありました。教育講演は東京理科大学薬学部の高橋希之先生の「低線量放射線の影響-直線仮説と放射線ホルミシス-」と題する講演でした。この講演は大屋大会長が以前に聞かれて大変感銘を受けたそうで、低線量被爆の影響を広島の原爆と原子力発電所の従事者のデータから分かりやすく説明していただきました。シンポジウムは「18F-FDG-PET検査における撮像に関するガイドライン」というテーマで行われました。3大会にわたるテーマであるEBMの集大成としてPET装置の標準化に向け、活発な討論が繰り広げられました。1日目の予定がすべて終了したあと参加者は、博多湾に向けて移動しました。懇親会は、博多湾を遊覧するレストランシップ・マリエラで催されました。湾内とはいえ船はかなり揺れましたが宴もたけなわになった頃、花火を見るためにオープンデッキに出ました。潮風がほろ酔いの肌に気持ちよく吹き抜けて行きました。その後、来年の27回大会の紹介をさせていただくことになり、10月に開催される第9回世界核医学ソウル大会にちなんでチマチョゴリの民族衣装を先頭に、かねてから用意していた大阪プロレスのマスクやUSJゆかりのスパイダーマンのかぶりもので登場しました。会場の皆さんは大阪人のノリを理解していただけたでしょうか。
2日目は特別講演として福岡大学病院の桑原康雄先生の講演があり、脳機能解剖、脳血流異常の意味するもの、脳疾患の病態評価と定量測定について統計画像を利用して講演されました。基礎講座ⅠとⅡは大会後すぐに実施される核医学技師認定試験に関連のある内容であったため参加者は熱心に聞き入っていました。
今回の総会学術大会のプログラムは例年と変わってシンポジウムを1日目に、基礎講座を最終日に開催したため、最後まで参加者が減少せず、活発な大会であったとの印象を持ちました。
最後にお忙しい中、丁寧に案内や説明をしていただいた大屋信義大会長はじめ、田中 稔実行委員長ならびに実行委員の皆様、ありがとうございました。
|