|
|
|
|
公立能登総合病院 放射線部 宮崎吉春 |
|
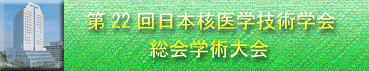 |
|
| 次期大会の実行委員長が今大会の印象記を書くことになっているという。当日大阪は、私たち北国の者をやり場のない暑さと異常なほどのクマゼミの騒音で歓迎してくれた。会場は千里ライフサイエンスセンターで、地下鉄を降りて2分の便利の良いところであった。しかも、第一会場と第二会場が廊下を隔てて隣同士と移動にも大変便利な会場設定であった。 医療経済並びに新薬開発が低迷している中、核医学だけが発展することは大変難しく、今が大切な充電期になる。この充電が如何になされるかによって、次世代における核医学の存在価値が決まって来るのだろう。今回のメインテーマ「核医学技術・次世代に託すもの」は、正にこのことを訴えているのだと思われる。 一般演題は、59題が発表された。その中で最も多かった分野は、最近関心度が高いOSEM法関連で7題が報告された。また、華やかな事が多々報告される中で、単純で古典的な検査法であるシステルノグラフィが、最近世情を賑わせている疾病の大変有効な検査法であるとの報告(新尾ら、帝京大)に、このような検査がもっとあるのではなかろうか。このような検査法を大切にし、底辺固めをすべきではなかろうかと思われた。 今回初めての企画であるディベートは、今関心のあるOSEM法に関することであった。新しい手法OSEM法と従来の手法FBP法を東軍西軍に分かれた演者がそれぞれの利点を述べ、会場の会員がどちらの方法はよいかを審判するものである。判定は、拍手の大きさを騒音計で測定するというユニークのものであった。結果は、企画者の期待に反し(?)、従来のFBP法が勝ってしまった。 特別講演では、西村先生(京都府立)が核医学画像は機能画像であるからこそ疾病の早期発見や予後の予測に役立ち、診療の効率化をもたらすであろうと話された。また、楠岡先生(国立大阪)は、行革が進む中の大学や国立病院の将来、医師の研修制度、診療報酬制度の改革などを中心に、予測のつき難い将来の医療体系について話された。 文化講演では、大谷先生(帝塚山学院大)が大阪人の特徴を東京人と比べながら、歴史的にどうしてこのような大阪人体質が生まれて来たかを分かり易く解いて下された。 ランチョンセミナーでは、竹内先生(西神戸医療セ)が、各人の脳SPECT像を標準脳に戻した後、その像に自動的にROIを設定する3DSRT法の有用性を演ぜられた(DRL)。石田先生(国立循環器病セ)は、心筋血流と心機能の両方を評価できるQGSの有効的な活用法を演ぜられた(NMP)。 卒後教育は基礎的な教育プログラムで、4演題が演ぜられた。中でも大西先生(日本メジ)は、最近よく用いられているが、中々中身まで理解し難い統計解析法を分かり易く説いて下された。 シンポジウムは核医学機能検査の現状と将来について4人の先生が熱弁を奮われた。中でも間賀田先生(浜松医大)の次世代のトレーサの話に大変勇気付けられたが、時間経過の遅さがもどかしく思われた。 懇親会は、近くの千里阪急ホテルで盛大に行われた。旧知の友、同級生、同窓生などが久しぶりに顔を合わせ、大いに懇親を深めた。アトラクションには、なんとあの宝塚歌劇のスター登場であった。さすがの美貌(でも、元は男役だったとか)、声力には圧倒させられた。ご当地ならではの演出であった。 この学会は、中村大会長、横野実行委員長を始めとする委員さん方の手作りの作品だと聞いた。大変な労苦を乗り越えての成果ではなかろうか。今は任を終えられ、大きな安堵感に浸っておられるのではないかと思います。 最後にこの項を借り、少しばかり来年の宣伝をさせて頂こう。来年は金沢。私たち実行委員は、参加してよかったと思われる会にすべく、エンジンを始動させました。これを読まれた先生、ぜひ今から来年の準備をして頂き、次期大会へ参加すると同時に「利家とまつ」の古都を満喫して頂きたい。 「金沢に来てたいね」。 |
|
 |
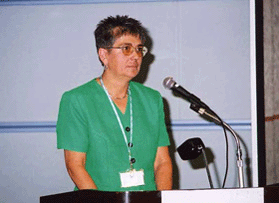 |
| いよいよ学会のスタートです。 大会長も若干緊張気味 |
米国の核医学技術の現状をお話いただきました |
 |
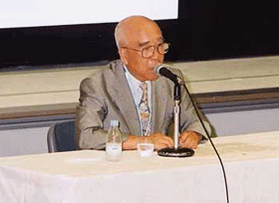 |
| 「未来に託す」核医学について 真剣な議論がありました |
大阪人の”いらち”ぶりを学術的に お話いただきました 納得でした |
 |
 |
| いわゆる”大ホール”ではなかったため、 むしろ活気を感じました |
大盛況でした |
 |
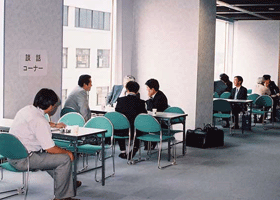 |
| 今年の受付担当は、”レベルが高い!”と 評判でした |
メーカー展示会場に隣接し、いつも満員でした |
 |
|
|
|
|