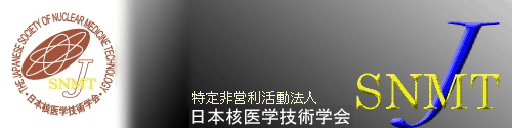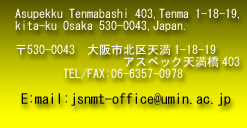|
企画戦略委員会・国際交流派遣委員会・PET委員会
各担当理事
福喜多 博義 |
| [理事挨拶] |
今年度から企画戦略委員会・国際交流派遣委員会・PET委員会を拝命致しました。理事長時代に解決できなかった様々なテーマについて今期中には完結する所存ですので、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
今年度から従前の「企画委員会」を新たに「企画戦略委員会」と改めました。主な活動として、現在審議中であります「放射性医薬品の取り扱いガイドライン」の策定に向け関連学会共同で進めおり、今年度中には提出される予定です。このガイドラインにより、今までグレーとされてきた業務内容が見直されると思います。また、これからの本学会の在り方を考えるとき、事業の企画立案にとどまらず、今抱える問題点を列挙し戦略的に解決をめざします。
国際交流派遣委員会では、主に国際会議への会員の派遣選考を行っていますが、その他、現在行われている学術大会時に開催しています韓国・台湾・日本における「国際学術交流フォーラム」を見直し、一歩発展させた組織としてASNMTを模索しています。国際交流活動を更に進めるため活動致します。
PET委員会では、日本核医学会PET核医学委員会と協力してPET研修セミナー(技師対象)の企画と開催を行っていますが、その他、関連学会と協力して、PET検査を取り巻く諸問題の解決に向け活動致します。
(国立国際医療研究センター国府台病院) |
 |
編集委員会担当理事
大屋信義 |
| [役員挨拶] |
本学会も国際的に、とりわけ東アジアの中心学会となるための活動を推進していくところです。会員の皆様も日本国内だけでなく、どしどし海外に出て行って発表のできる人材となって頂くのが望ましいところと考えています。最近になって、少しずつ投稿も増えてきている状況ですが、やはり原著での投稿が少ない点が気がかりです。オンライン投稿も考えておりますが、もう少し時間がかかるようです。
日々の臨床業務でたいへん忙しいことは、重々理解しておりますが、臨床業務に追われるだけでは、自分自身の仕事の楽しみがなく、意欲も低下するばかりです。ぜひ研究に精を出して頂き、仕事の楽しさを実感して頂き、論文を完成させて、投稿頂けるよう切にお願い致します。編集委員一同、査読が追いつかないような状況になることを楽しみにお待ちしております。
(九州大学) |
 |
生涯教育委員会担当理事
長木昭男 |
| [生涯教育委員長に就任して] |
平成20年度より本会の理事に就任し、2年の任期を生涯教育委員会の委員長として務め、再びこの委員会委員長を拝命しました。この2年の間には、第29回総会(旭川)および第30回総会(大宮)での卒後教育プログラム、シンポジウム、合同薬剤調製セミナーの3つプログラムをそれぞれ企画し実施しました。
卒後教育プログラムは、核医学技術を臨床で実践するために必要とされる基礎的な知識を得ることを目的としています。またシンポジウムは核医学技術の現状において早急に解決すべき内容をテーマにしています。第30回総会では2009年の核医学技術に掲載されたRI医薬品の取り扱いに関する調査研究WGの報告を受けて診療放射線技師による放射性医薬品の取り扱いについてシンポジウムを開催しました。安全な薬品調製と事故防止のためには、合同薬剤調製セミナーもますます充実した内容にする必要があると考えます。
核医学を担当する技師には、放射性医薬品や画像の撮像技術、さらに放射線管理まで幅広く知識が要求されます。生涯教育委員会では、核医学技術の動向を検討しながら会員の皆様の役に立つ情報を提供したいと考えていますので、今後も皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いします。
(倉敷中央病院) |
 |
核医学技術セミナー担当理事
木田哲生 |
| [新理事の挨拶] |
このたび、本学会の理事に推され、セミナー担当理事を拝命いただきました滋賀医科大学医学部付属病院 放射線部 木田 哲生と申します。微力ではありますが、核医学技術セミナーの成功に向けて実行委員会・学会事務局と協調して進めてまいります。
本セミナーは、当番制により企画から準備、運営までを地方会が担当します。その目的は、二つあると思っています。第一は、レベルアップのための核医学技術および核医学診断の研修です。第二には、地方会会員諸氏に運営の参画による地方会の活性化です。過去の盛会の歴史を継続して受講される方、運営に当られる方の双方にとって成果多きセミナーの実現を目指していきます。
また、その他にも諸先輩の理事・監事、事務局の皆さまのご指導を仰ぎながら本学会を会員の皆様にとってより魅力的な学会にしたいと考えております。さらには、核医学技術の研鑽に留まらず、国際交流をはじめ、社会的責任となる医療技術の向上、放射線管理などを通じて社会貢献ができる学会を目指していきたいと思っております。そこに核医学セミナー等の研修事業が同調することを望んでおります。
会員の皆様には本学会事業および本セミナーへのご協力の程よろしくお願いいたします。
(滋賀医科大学医学部附属病院) |
 |
核医学専門技術者認定担当理事
菊池敬 |
| [ご挨拶] |
引き続き、専門技術者認定委員長を務めさせていただくこととなりました。また、当学会からの核医学専門技師認定機構執行役員も兼務致します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご存じの通り、本学会では核医学の専門技術者を認定する制度をいち早く導入し、現在まで関連学会からも高い評価を頂いております。また、多くの専門技術者が施設内において、更には地域内におきましても診療、研究、教育のそれぞれの環境でリーダー的立場に立ち、活躍されているところであります。
今日の核医学診療では、他のモダリティとの融合画像やエビデンスのある定量情報の提供、核医学治療の導入などに伴い、より幅広い知識と技術が求められております。装置の保守点検管理や放射性薬剤の管理体制については、より安全性が担保された核医学診療の提供が社会的にも求められる背景にあります。この状況に鑑み、最新の医療技術に対応した画像情報の提供、安全性や国民の福祉と社会の発展に寄与することを目的に、本学会を含む複数関連学術団体から構成する核医学専門技認定機構も平成18年に立ち上がりました。
昨年4月には厚生労働省医政局長通知による「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について 」が出されたことから、チーム協働体制による核医学診療については、より専門技術者や専門技師の果たす役割は大きいかと推察いたします。
会員の皆様におかれましては学会ならびに認定性に関する趣旨のご理解をお願い致しますとともに、認定をまだ習得されていない会員の方々には積極的な認定取得を目指されますことをお願い致します。
(北里大学病院) |
 |
学術委員会担当理事
小野口昌久 |
| [学術委員会担当理事に就任して] |
この度,渡邊理事長より理事を拝命致しました。浅学非才ですが,新理事長の下,気持ちを新たにして何ができるかを熟慮し会員の皆様に少しでも貢献できるよう努力する所存でおります。
今回,学術委員会の担当を指名されましたが,当委員会の主な仕事は研究助成事業と調査研究のためのワーキンググループ(以下,WG)の編成となります。研究助成は年1回1件ですが,是非,積極的に有効利用して頂きたいと思います。また,現在「がんFDG-PET撮像法の標準化WG(班長:福喜多博義)」,「核医学で使用する密封線源の安全取り扱いに関するガイドラインの検討WG(班長:金谷信一)」,「RI医薬品の取り扱いに関する調査研究WG(班長:杉林慶一)」の3つのWGが活動を継続しておりますが,その他に,クリアランス制度と放射化物の規制を取り入れた放射線障害防止法の改正,あるいは厚労省による技師の「読影の補助」と「検査の説明・相談」を明確化したことから,まずは担当窓口を設け,本学会を含めた他団体との協調および対外的な動向も見据えながら新WGを立ち上げる方向で今後進めていく予定でおります。
核医学技術の発展に向けて微力ながら貢献する所存でおりますので,皆様のご指導,ご鞭撻の程,宜しくお願い申し上げます。
(金沢大学医薬保健研究域保健学系量子診療技術学分野)
|
 |
表彰・総務(学会広報)・渉外委員会担当理事
森一晃 |
| [役員挨拶] |
平成22年度から表彰、総務(学会広報)、渉外委員会を担当しています。昨今の核医学診療では、Sr-89、Y-90による内用療法の認可に続きI-131による外来治療が可能になるなど、厳格な放射線管理が求められる場面が増えてきました。治療実施にあたっては実施基準、ガイドラインを遵守する必要があります。こうした新しい基準や変更点に関する情報を迅速かつ正確に会員へ周知することが学会として重要な責務と考えます。また、クリアランス制度およびPET用サイクロトロンによる放射化物の法制化、技師による放射性医薬品の調製といった課題については1つの団体で決められることではなく、医療関連学会等団体が合同で取り組む内容となっています。各団体が協調性を持ち、意見を集約したうえで、現状の医療に有益となるような合理的な法整備が望まれるところです。
本学会の表彰事業には、学会活動に貢献してくださった方々を表彰するともに、優秀な論文に対して表彰する事業もあります。しかし、ここ数年は対象となる論文数が伸び悩みの傾向にあります。学会誌の充実と事業の活発化、また自己研鑚の意味でも、いままでより積極的な論文投稿を会員の皆様にお願いしたいと思います。
今後とも会員の皆様のご指導、ご協力ほど、よろしくお願いします。
(虎の門病院) |
 |
総務委員会庶務・組織検討委員長・事務局長担当理事
横野重喜 |
| [役員挨拶] |
今年度より、総務委員会庶務担当、組織検討委員長ならびに事務局長を兼務いたします。いずれも学会の足元を固めるための役職と理解しておりますので、可能な限り職責を果たす所存であります。さて、日本核医学技術学会は平成21年4月に特定非営利活動法人となり、社会に認知された法人となりました。ここ数年の活動を振り返れば、技術的なガイドライン作成や最新の核医学技術を解説した書籍の発刊等、医学系法人の責務として社会に情報発信を行ってきました。今後もこの流れを減速させることのないよう役員一同舵取りを行っていかなければなりません。また、本学会の会員数の継続的な増加は、核医学を担当する技師の技術的な向上機運の高まりと理解しており、会員からのニーズを柔軟に取り入れる仕組みも重要と認識しています。一方で核医学を取り巻く環境の変化は、企業からの支援にも影響を及ぼしつつあり、学会活動を支える資金面における足元の調整についても今後の課題といえます。以上のように若干の課題はありますが、本学会の活動が少しでも国民の医療福祉の向上に寄与できるよう支えてまいりますので、関係各位のご協力をよろしくお願いいたします。
(宝塚市立病院) |
 |
財務・広報・財務関連広報担当理事
西村圭弘 |
| [理事挨拶] |
皆さん、こんにちは。このたび、日本核医学技術学会財務担当理事に就任いたしました西村圭弘(国立循環器病研究センター)です。日本核医学技術学会は核医学技術セミナー、核医学技術学会総会学術大会のセミナー受講、学会発表等で大変お世話になりました。このような学術学会の理事に就任できましたことを大変誇りに思っております。また同時に、この歴史ある学会にどの様に貢献できるか、自己の知恵と体力の発揮しどころと考えております。体力では学生時代に所属していましたワンダーフォーゲル部の山登りに最近再びチャレンジしています。これまで、八ヶ岳を中心に山に登ってきました。目標は南アルプス最高峰の北岳とそれに続く3,000メートル級の稜線にトライすることです。
さて核医学技術学会の財務状況は、近年の不況により大変厳しい運営が続いております。しかし、核医学技術学会として学会誌の充実、学術総会の円滑な運営、国際交流、研究助成など核医学技術の発展には欠かすことのできない事業を進めて行く必要があります。事業とその予算を、核医学技術の発展と社会的貢献度を考え、有効な事業の選択と予算、人的資本の集中により効率的に運営して行く重要性が、これまで以上に高まっていると考えています。財務の仕事は初めてですが、これらの難問を体力と気力で粘り強く取り組んでいきます。会員の皆さんの学術活動の積極的な参加を期待しています。
(国立循環器病研究センター) |
 |
出版委員会担当理事
片渕哲朗
|
| [出版委員長に就任して] |
最近ある雑誌で、「日本は欧米諸国より劣っている」「もともと日本は欠点だらけの国だ」などという考えを、われわれ日本人が潜在的に持っているために、日本の国力が低下してきていると述べていました。そうでもないような気もしますが、確かに自信は失いつつあるように感じます。では、この自信を取り戻すにはどのようにしたら良いでしょうか。自分というものをそのまま受け入れるだけで充分自信が持てるような気がします。「私は現時点でのベストを尽くしている」「自分のこれまでやってきたことが役に立っている」などのように自分の長所に目を向ければきっと多くの事柄が見付かるでしょう。核医学においても正しい検査をするには、携わる技師の知識が要求されます。学識を広げるために自ら勉強することで、多くの自信を持つことができます。
ところで、昨年10月に本学会より「核医学画像処理」を出版いたしました。核医学関係で画像処理に絞った専門書がなかったため、お陰で好評を得ております。これまで「核医学総論」「PET技術マニュアル」も本学会から刊行しており、出版事業が本学会の大きな業務になりつつあります。核医学技術に関する自信を持つには、このような学会が出版する専門書を利用することが最適です。核医学技術を担うわれわれが自信を持つことにより,我が国の核医学技術のレベルを底上げし,核医学全体の活気を生むことも可能なのです。
皆さんと一緒に歩く核医学技術学会と思っています。
(岐阜医療科学大学保健科学部放射線技術学科)
|
 |
電子情報管理委員会担当理事
大阪肇
|
| [電子情報管理委員会委員長に就任して] |
本年度より電子情報管理委員長を拝命させていただきました大阪肇と申します。今委員会は、歴代委員長の藤田透先生、齋藤京子先生、渡邉浩先生、小野寺敦先生らを中心に委員方々が築き上げたホームページの管理・運用システムや会員IDによる一元管理、理事会・評議員会・各委員会のメーリングリストの運用・管理、さらには総会学術大会オンライン演題登録システムの作成、その他各事業の連絡などを主に行なっております。常日頃より会員の皆様には御理解・御愛好いただき感謝申し上げます。当然ながら、会員の資質の向上、会員への情報提供を念頭に入れた作業を行ないながら、かつ社会に広く浸透している電子情報網においては、まさに本学会の「顔」とも言えるホームページを通じて、本学会の目的にもあります「核医学技術学の発展を通じ、核医学の知識・科学技術の向上、普及啓発、良質な医療の提供につとめ、国民の医療福祉の向上に寄与すること」が達成されるよう常時検討しながら務めさていただいております。今後も作業のさらなる強化を目指し、システム構築を行なってまいりますので、皆様の変わらぬ御理解・御愛好の程、宜しくお願い致します。
(秋田県成人病医療センター) |
 |
監事
齋藤京子 |
| [監事として] |
平成22年度からの2年間を引き続き監事の任を仰せつかりました。理事会,事務局の尽力と会員の皆様の活力により,本学会では特定非営利活動法人化,日本核医学会との学術総会の合同開催などの新しい道を着実に進んでおります。学会と会員の思いはひとつ,「核医学技術学の発展を通し、良質な医療の提供につとめ、国民の医療福祉の向上に寄与すること」です。その目的達成のために,学会は核医学技術学の啓発活動を企画・実施し,会員は自己研鑽の場として学会の諸事業を積極的に利用・活用することが大切と考えます。渡邉新理事長のもとに理事会はさらなる学会の進展を目指してスタートしました。監事として理事会運営を見守り,理事の業務執行および法人の財産状況を誠実に監査し,微力ながら学会の発展に努めたいと存じます。学会の活動・事業に会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
(北里大学医療衛生学部) |
 |
監事
中村幸夫 |
| [挨拶] |
今年度から松本政典前監事の後任となりました中村です。本学会の前身である核医学技術研究会発足以前から地方会の事務局を始めとする運営に携わってまいりました。全国規模の学術大会となった核医学技術研究会第1回総会学術大会が高坂先生のもと京都で開催されました。会場が公的施設であったためか融通が利かず開錠時間まで我々実行委員も外で待たされたことなど鮮明に覚えています。それから30回目を昨年迎え感慨深いものです。
数年前よりエビデンスに基づいたガイドライン作り、各モダリテイでの専門技師認定制度、医療の安全など我々を取り巻く環境も日々刻々と変化しています。そのような環境に対応してゆく中で最近は特に時の流れの速さを感じます。本学会も役員交代が行われ渡邉理事長をはじめ新執行部が発足しました。核医学会との関係強化を始め他団体との共同作業が重要となってきております。また、海外交流事業の一環として東アジアを視野に入れた学術合同開催も文化交流といった意味で特定非営利活動法人の役割の一つと考えます。
昨今の景気不況もあって関連会社の事業縮小・統廃合などの余波のためか学会財政にも影響を及ぼしてきている。こうした中で学会執行部にはバランスのとれた事業展開を望むところです。会員を代表する監事として今までとは違った目線で役目を果たしたいと思います。
(大阪大学医学部付属病院) |